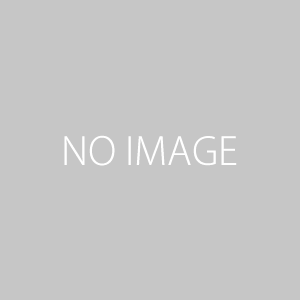〔左官動画〕「土磨き」「洗い出し」技術研修会@伊勢
2024年11月23日、三重県左官業組合連合会伊勢支部による技術研修会が行われました。
研修会では、日本左官会議正会員でもある西川和也さんが、石灰を入れない色土だけで仕上げる「土磨き」を指導しました。
作業の合間には、「洗い出し」のブラシ使いのコツも披露。効率よく作業を進めるコツを伝授してくださいました。
伊勢土磨き
土磨きとは、大津磨きのように石灰を使わず、土だけを使って、磨く仕上げです。西川さんは、これを大津磨きの元ではないかと考えています。工程の考え方は大津磨きと一緒です。
今回の下地の材料は、地元の田んぼの床土(とこつち)と、蔵を解体した時の古土を混ぜたもの。0.7〜1mmの厚みで2回塗って、その都度伏せ込み、表面に少し艶が出るまでこなした状態になっています。


乾いた下地(中塗り)の上に、色土(稲荷山)を伏せ込んでいきます。仕上げには、粘土分が高い土が適しています。保水のため、時期によっては紙スサを加えます。
色土の伏せ込みは3〜4回行って、まんべんなく延ばしていきます。
2回目に塗る色土の厚みは0.2〜0.5mmで、艶が出るまで地金の鏝で伏せ込みます。さらに半焼きまたは油焼き鏝でこなします。仕上げは本焼き鏝で通します。


材料に石灰が入っていないので、急激に乾燥しません。
「磨きの仕事の時は普通、仕上げるまで飯食えないけど、土磨きだったら、お昼に行けます」と、西川さんは言います。
洗い出し
洗い出しは、砂利や砕石などの種石をモルタルやコンクリートに混ぜ込み、表面を軽く洗い出すことで種石を露出させる仕上げです。
古くから庭や外構、土間仕上げなどに使われており、素朴ながらも風情があります。
種石の大きさや色を変えることで、多彩なデザイン表現が可能となり、実用性と美観を兼ね備えています。



今回は、セメントモルタルに種石を入れたものを塗りつけて、ブラシでノロを取る方法でした。下塗りのモルタルには、保水のためにメトローズを入れています。
ブラシの腰をうまく使うことで、種石は残したまま効率よくノロを取り去ることができます。
番外編もぜひ!
研修会には、日本左官会議からも数名の会員が参加しました。
そのなかから、長田幸司(議長)、川口正樹(副議長)、小林隆男(正会員)の作業風景をご紹介します。